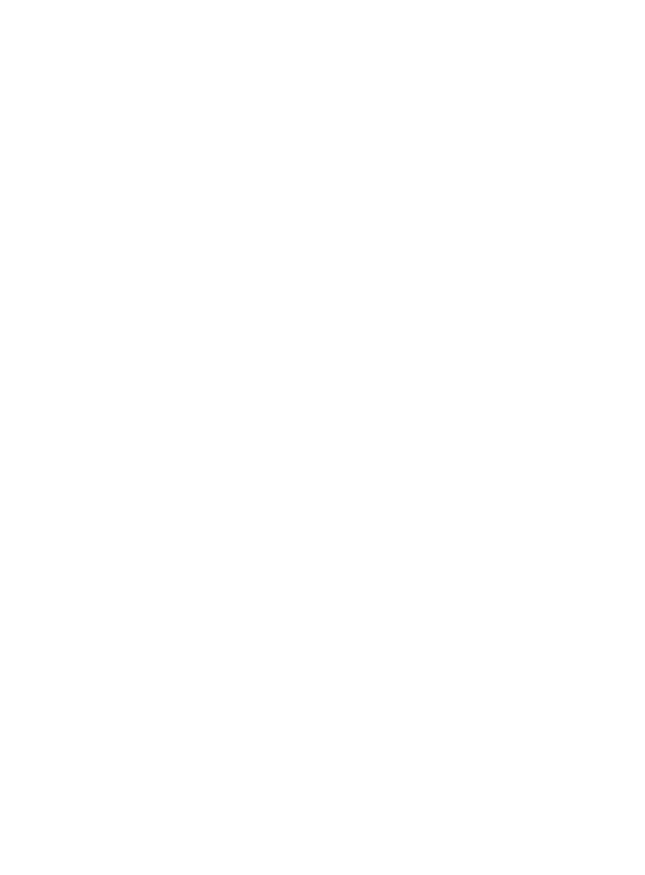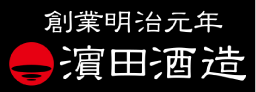かつて薩摩藩の栄華を支え続けた、串木野金山。
その跡地に「継承の蔵・薩摩金山蔵」はある。
350年余り掘り続けられた、
総延長120km に及ぶ坑洞内は、年間を通して
気温や湿度が一定で、貯蔵・熟成にもってこいだ。
天からの授かり物であり、また、歴史からの授かり物。
そして、霊峰「冠嶽」の伏流水。
それを私たちは守り続けてきた。
この蔵での焼酎づくりでは、幻と言われる独自の
「黄金麹」を用いた製法も行われている。
すべては、継承の先に生まれたに過ぎない、
ともいえる。
だが、その積み重ねこそが「唯一無二」の
味わいをもたらす。
この地域・文化の物語への共感から生まれた蔵。
国内のみならず、海外の人々をも魅了していく酒。
原料や製法を継承しながらも、
深化させ、磨き上げることで。
20年目の金山蔵は、
継承の力で未来へ、
そして世界へ挑みます。
継承の力で未来へ、
そして世界へ。
Company Statement
金山蔵の歴史
History
かつて薩摩藩を、明治維新を支えた場所で。
「唯一無二」の本格芋焼酎が育まれていく。
その場所に歴史あり。
坑洞と貯蔵空間。