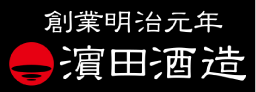串木野金山の始まり

薩摩藩の中でも有数の規模を誇った霧島市横川町の「山ヶ野金山」は、1643年(寛永20年)、江戸時代初期に幕府の命により閉山となりました。これにより行き場を失った多くの鉱山職人たちを受け入れるべく、新たな鉱脈の開発が急がれました。
そして1652年(承応元年)、串木野の地で新たな金鉱脈が発見され、1660年(万治3年)には本格的な採掘が始まりました。こうして誕生したのが「串木野金山」です。開発にあたったのは、島津家の家臣・八木主水佑元信(やぎ もんどのすけ もとのぶ)と伝えられています。
串木野金山周辺は火山帯に位置し、地下深くに存在する熱水によって、金や銀を含む鉱脈が形成された地質環境にありました。
金山は金を掘るだけじゃない

串木野金山は、金鉱石を掘るだけの場所ではありませんでした。そこには多種多様な役職があり、鉱脈を見つける「山師」、掘削を担う「坑夫」、掘り出した鉱石を運ぶ「運搬人」など多くの職人たちが関わっていました。彼ら一人ひとりの技術と労働によって、金山は支えられていたのです。
まるでひとつの町のように、人々はそれぞれの役割を果たしながら、「未来を支える金を掘り出す」という誇りを胸に、日々の仕事に情熱を注いでいました。こうした多様な営みこそが、金山を支え、そして串木野の繁栄にもつながっていったのです。
串木野金山の今

300年以上の歴史を持つ串木野金山は、役目を終えた後も、静かにこの地に佇んでいます。
現在は坑道の一部が「薩摩金山蔵」として活用されており、安定した気温と湿度を生かして、焼酎を熟成させる蔵として生まれ変わりました。
近年では、学術的な調査も進み、坑道構造や鉱脈の分布、当時の生活環境などが次第に明らかになってきています。串木野金山は単なる産業遺産ではなく、まちの原点であり、技術や文化を現代に伝える「生きた歴史資源」でもあるのです。
焼酎造りを通じて、金山の歴史や文化を「継承」し、未来へと語り継いでいく。それが、今の串木野金山の役割です。
Information
●薩摩金山蔵のこれまでとこれからをご紹介する20周年特設ページはこちら