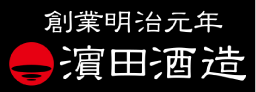日本の津々浦々にある神社には様々な神様が祀られており、「パワースポット」としても人気が高く、国内外から多くの参拝客が訪れる観光地です。今回ご紹介するのは、「焼酎神」。先日、鹿児島県南さつま市にある竹屋(たかや)神社で、祭神の4柱を「焼酎神」として祀るための式典が行われました。4柱というのは、「火明命(ホアカリノミコト=海幸彦)・火蘭降命(ホツセリノミコト)」・「彦火火出見命(ヒコホホデミノミコト=山幸彦)と豊玉姫命(トヨタマヒメノミコト)の4人の神様を指します。「火明命」「火蘭降命」「彦火火出見命」の3神は、酒造の神様でもある木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)より、燃え盛る火の中で生まれ、いずれも名前に「火」がついていることから、蒸留酒の神・焼酎の神様として、海神の娘である「豊玉姫命」は、焼酎でいえば、蒸留技術やサツマイモが海の彼方からもたらされたと考えられることから、4人の神様がひとつの神社で祀られている竹屋神社を「焼酎神社」と呼ぶことになったそうです。逆境に立ち向かい、自らの手で未来を切り開き、海外の文物や技術を巧みに取り入れ、今日に至る日本を築いてきた歴史が秘められている竹屋神社は、焼酎造りに携わる方々や、焼酎が好きな方、この4柱のパワーで満ちたスポットを訪れたい方で賑わうことが期待されています。
焼酎蔵の中にもパワースポット!‐薩摩開運神社–
〝焼酎″繋がりのパワースポットといえば、この薩摩金山蔵にある「薩摩開運神社」です。坑洞内にあり、島津家第17代当主島津義弘公を祭神として祀る神社として、薩摩金山蔵が誕生した平成17年4月に加治木精矛神社から分祀(ある場所に祀られている神を、別の場所でも祀ること)されました。島津義弘公は、戦国時代から安土桃山時代にかけての薩摩を代表する武将で、1600年の関ヶ原の戦いの時、西軍石田三成とともに徳川家康軍と戦いますが劣勢に立たされた義弘公は、堂々と敵陣のど真ん中を突破し、薩摩へ戻ってきました。後に「島津の退き口」として語り継がれることになる逸話があります。
今回、ご紹介した2つのパワースポット。4人の神様と島津義弘公。いずれも、目に見えないエネルギーに満ちた神社です。秋の旅行で、九州方面へ行ってみようかなと計画中の皆様、焼酎に関連する聖地で、お疲れの心に癒しとパワーを。
Information
■薩摩開運神社へのアクセスはこちら
■竹屋神社についてはこちら