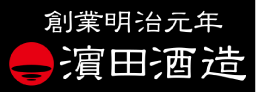焼酎造りの歴史を築いた蒸留技術のルーツとは

ユネスコの無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」。焼酎造りに受け継がれている、伝統的なこうじ菌を使った酒造りの技術と知識が評価された、とても嬉しいものです。
では、焼酎造りはどのようにして伝来し、鹿児島の地に根付いたのでしょうか。その背景に注目し、焼酎の魅力を探ります。
焼酎造りの特徴のひとつが「蒸留工程」を持つことです。蒸留器は紀元前3000年頃、古代メソポタミアで発明され、その後蒸留酒の技術が確立し世界中に広まりました。アジアへは13~14世紀、元の時代の中国に伝わり、諸説ありますが、のちに泡盛の製造を発展させた琉球王国に伝わったとされています。その後、九州へと伝来した経路については、琉球、朝鮮半島、中国経由などさまざまな説がありますが、この蒸留技術の伝来によって、焼酎文化の土台が築かれる重要なきっかけとなりました。

米焼酎から芋焼酎へ。さつまいもの伝来が生み出した、鹿児島の焼酎文化

蒸留技術が南九州で定着し、焼酎が誕生した背景には、温暖な気候と海外との活発な交流が挙げられます。適した環境に加え、いち早く情報や文化を取り入れたことで、蒸留技術も進化を遂げたと考えられます。
焼酎造りの初期は、米を原料とした焼酎が主流でした。しかし江戸時代の薩摩藩では米不足が発生。その際に伝来したのが鹿児島の土地や気候に適していた「さつまいも」でした。これをきっかけに「芋焼酎」が誕生し、今日へと続く焼酎文化が形づくられていきました。
焼酎に関する記録は、1546年に山川港を訪れたポルトガル人が「米からつくるオラーカ(蒸留酒)」があることを記しているほか、鹿児島県伊佐市の神社には、「焼酎」という言葉を使った落書きが残されています。こうした記録から、鹿児島の焼酎には500年におよぶ歴史があると考えられ、時代を超えて今もなお愛されるお酒となりました。
焼酎の伝統を感じる一杯、「兼重源酒」で味わう米と芋の魅力

焼酎の歴史に思いを馳せながら、一杯味わってみませんか。おすすめは、長期甕貯蔵で仕上げられた「兼重源酒」です。
米を白麹で仕込み、米の香りとふくらみのある味わいが楽しめる本格米焼酎「兼重源酒(米)」。そして、さつま芋を白麹で仕込み、甘く濃醇な口当たりからドライでキレのある後味へと変化する奥深い味わいの「兼重源酒(芋)」。どちらも蒸留工程の最初にでてくる「初留取り」を長期甕貯蔵した貴重な焼酎です。ストレートやロックでそれぞれの香りの違いを堪能しながら味わうのがおすすめです。
500年にわたる焼酎の歴史を感じながら、その魅力を心ゆくまでお楽しみください。
Information
■記事内の商品
●長期甕貯蔵 兼重源酒(米)
内容量:500ml
容器:瓶
原材料名:米(国産米)/米麹(国産米)
麹:白麹
アルコール分:43度
【商品説明】
米の香りとふくらみのある味わい
長期甕貯蔵した本格米焼酎
米を白麹で仕込み、減圧蒸留しました。
蒸留するときに最初に出てくる「初留取り(しょりゅうどり、『はなたれ』とも)」を長期甕貯蔵した希代の本格米焼酎です。
アルコール度数43度。濃厚な口あたりと共に、熟成された米の香りと甘みをお楽しみください。
・商品についてはこちら
・オンラインショップでのご購入はこちら
●長期甕貯蔵 兼重源酒(芋)
内容量:500ml
容器:瓶
原材料名:さつま芋(鹿児島県産)/米麹(国産米)
麹:白麹
アルコール分:42度
【商品説明】
かつては蔵人の楽しみだった『はなたれ』をじっくり長期甕貯蔵
鹿児島県産のさつま芋を白麹で仕込み、常圧蒸留しました。
蒸留するときに最初に出てくる「初留取り(しょりゅうどり、『はなたれ』とも)」を長期甕貯蔵した、希代の本格芋焼酎です。
アルコール度数は42度。はじめの口あたりは甘く濃醇、後口はドライな辛口に変わります。
・商品についてはこちら
・オンラインショップでのご購入はこちら